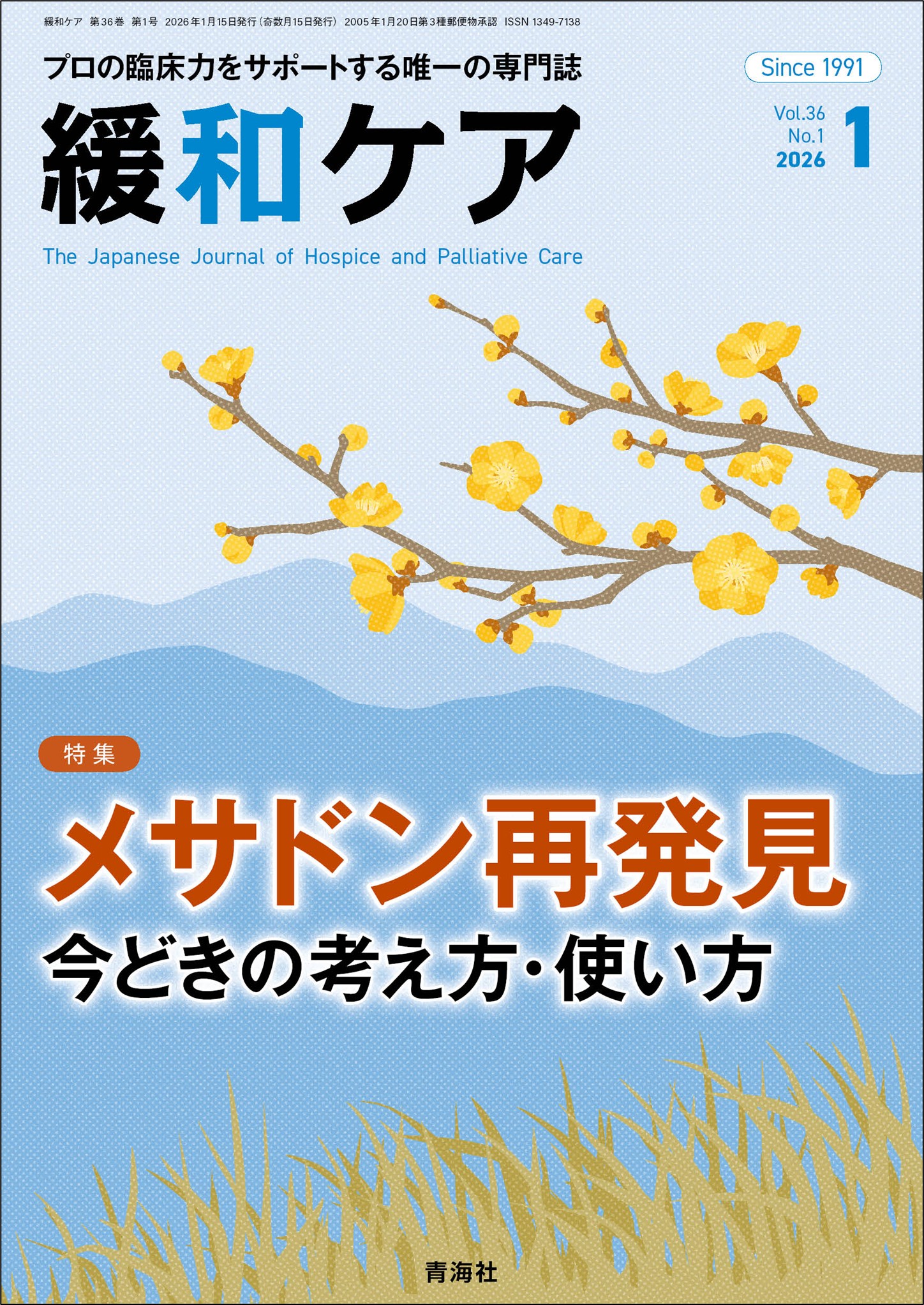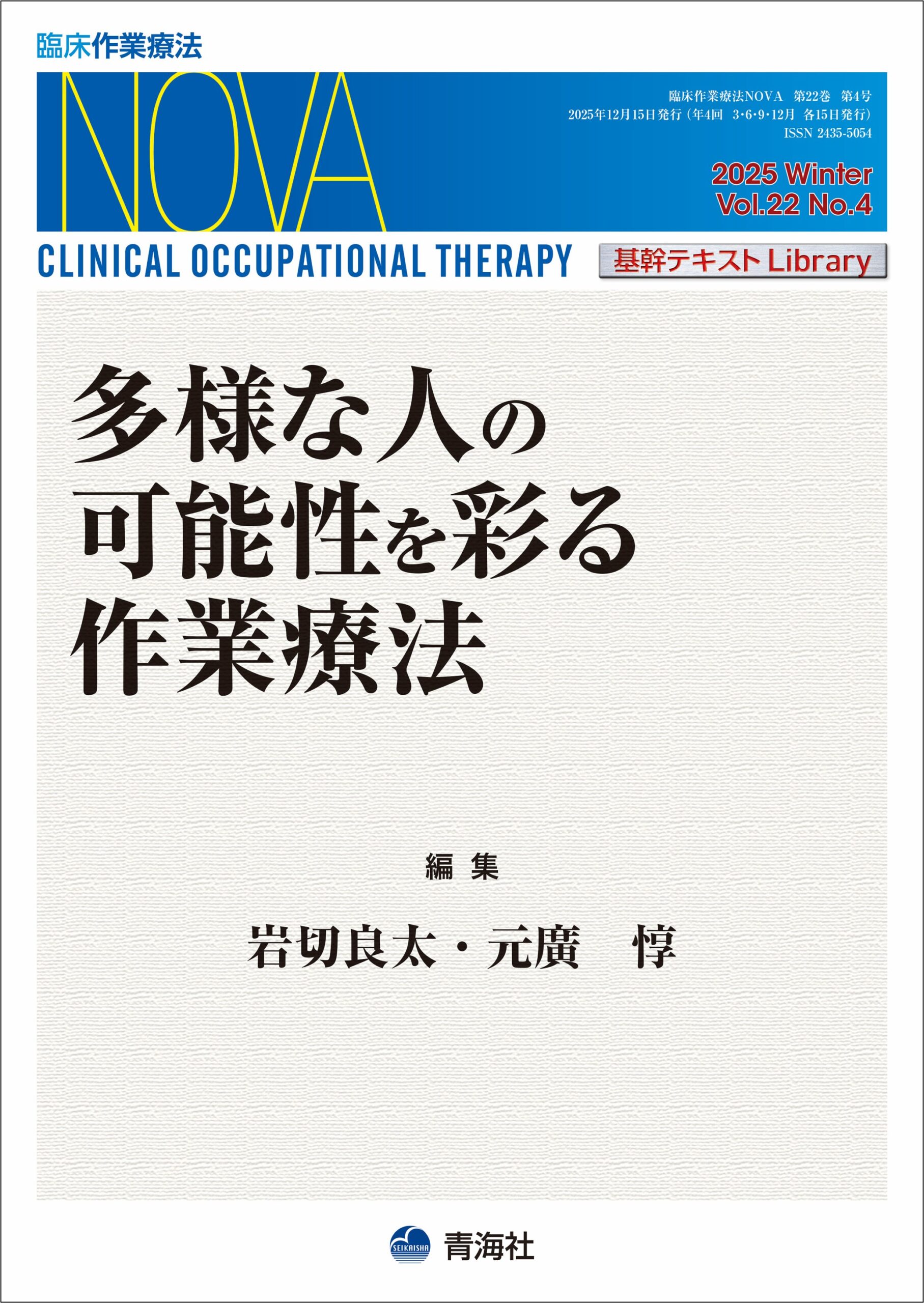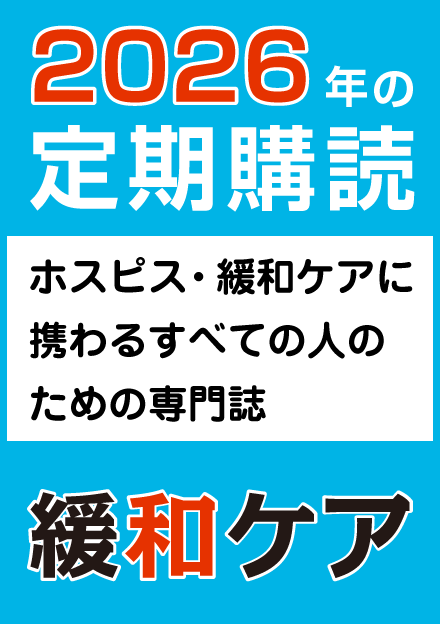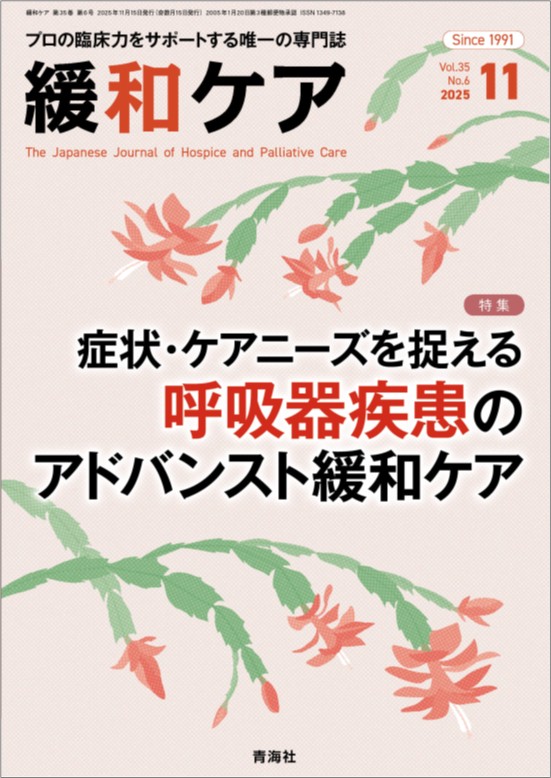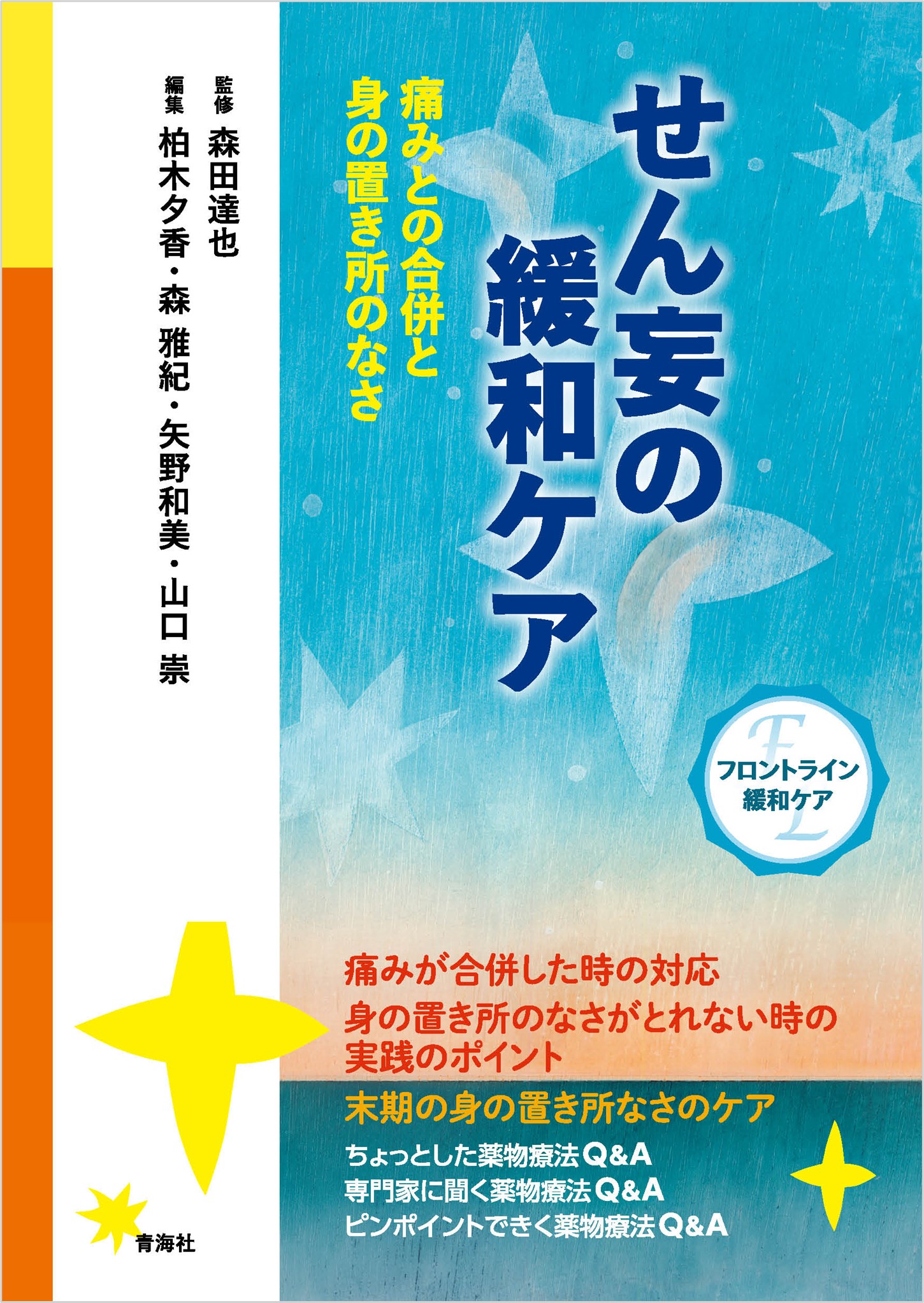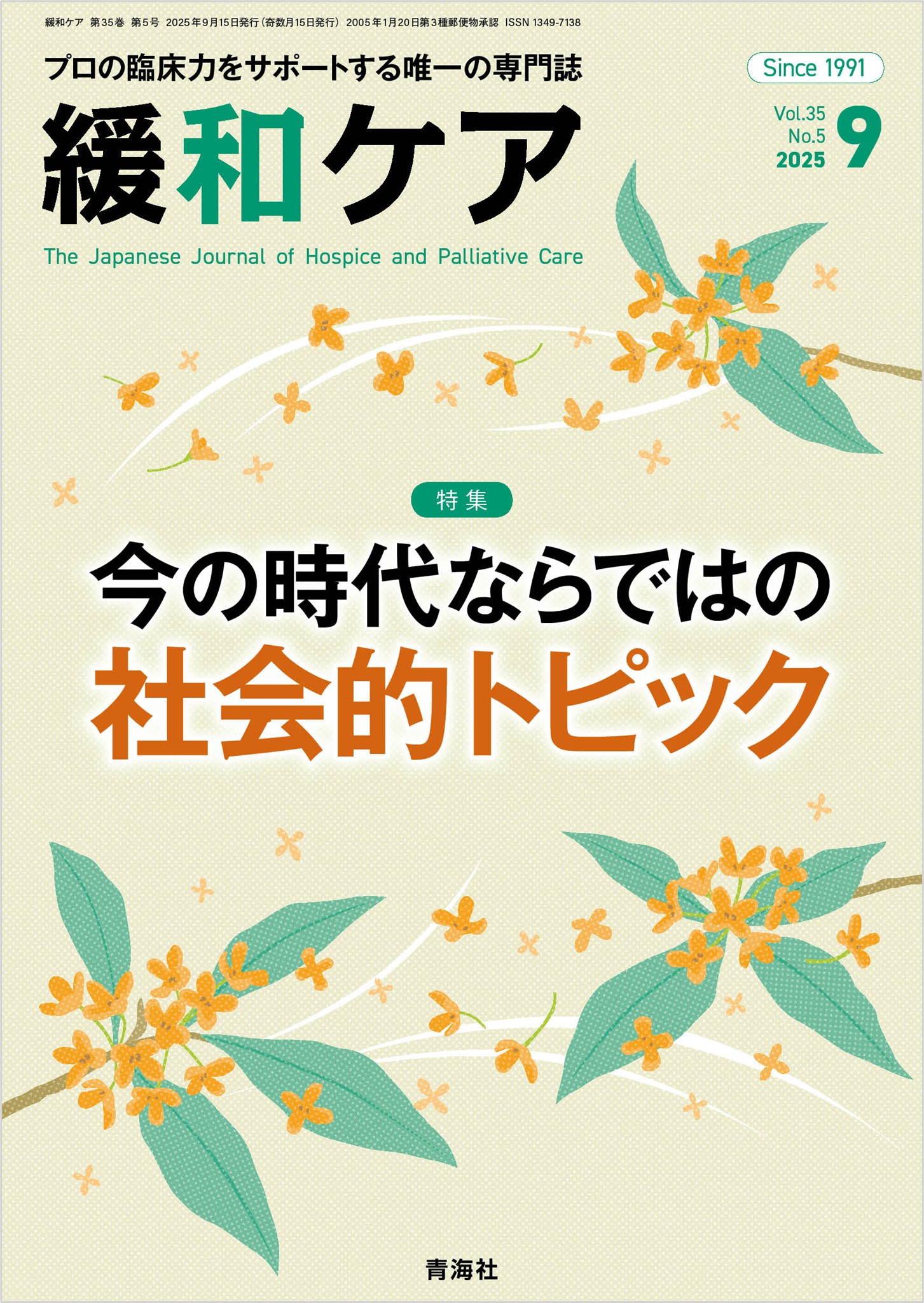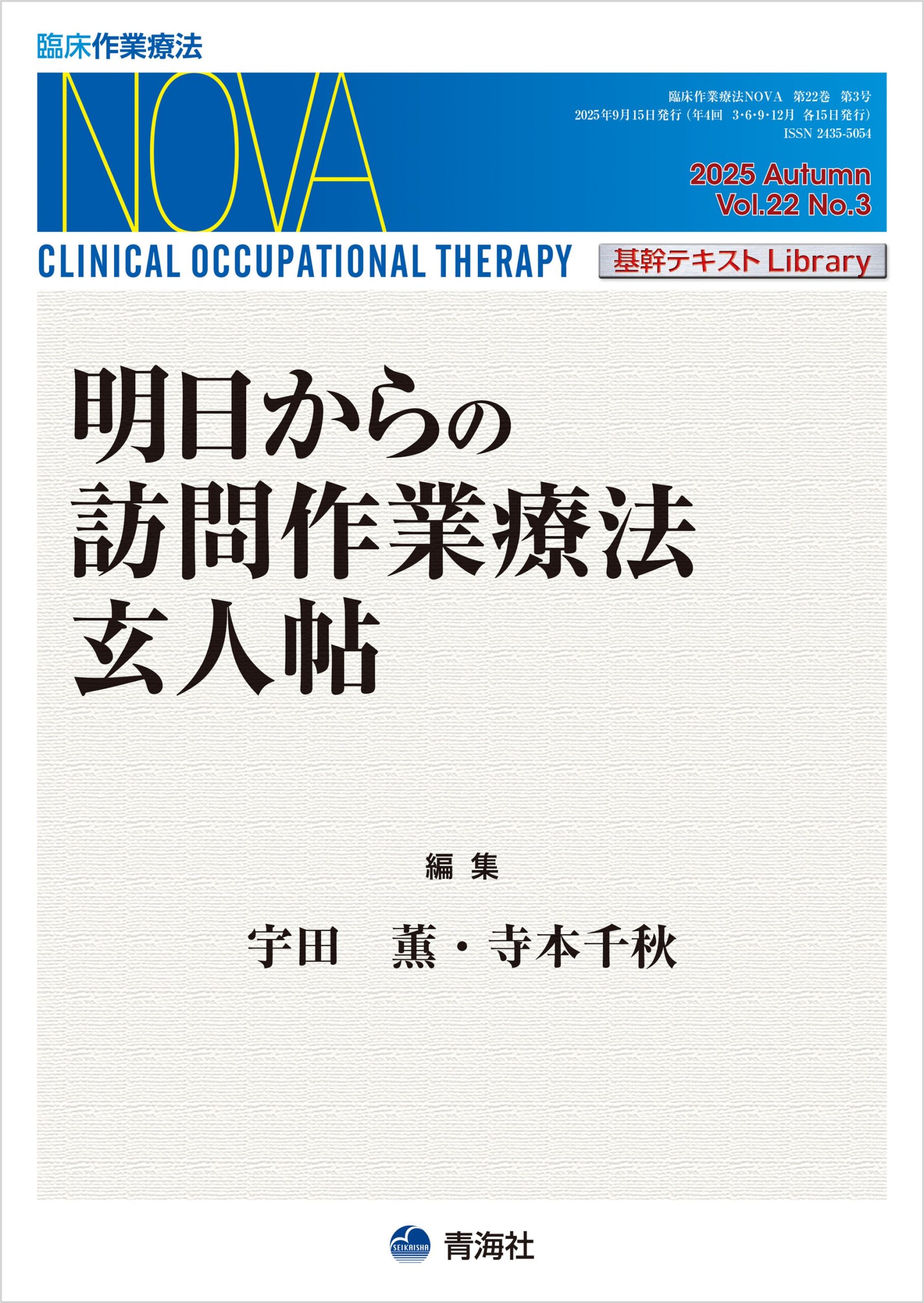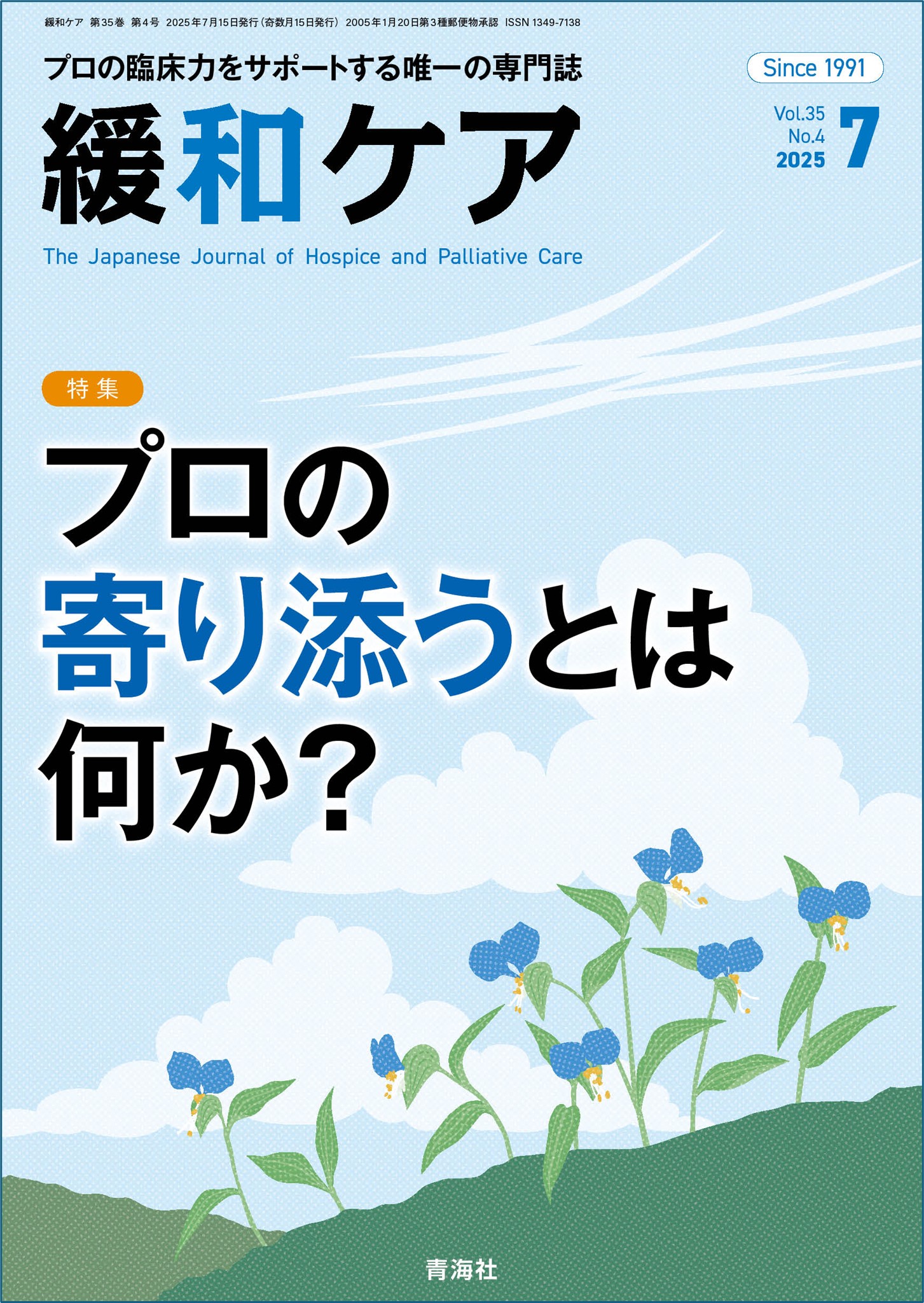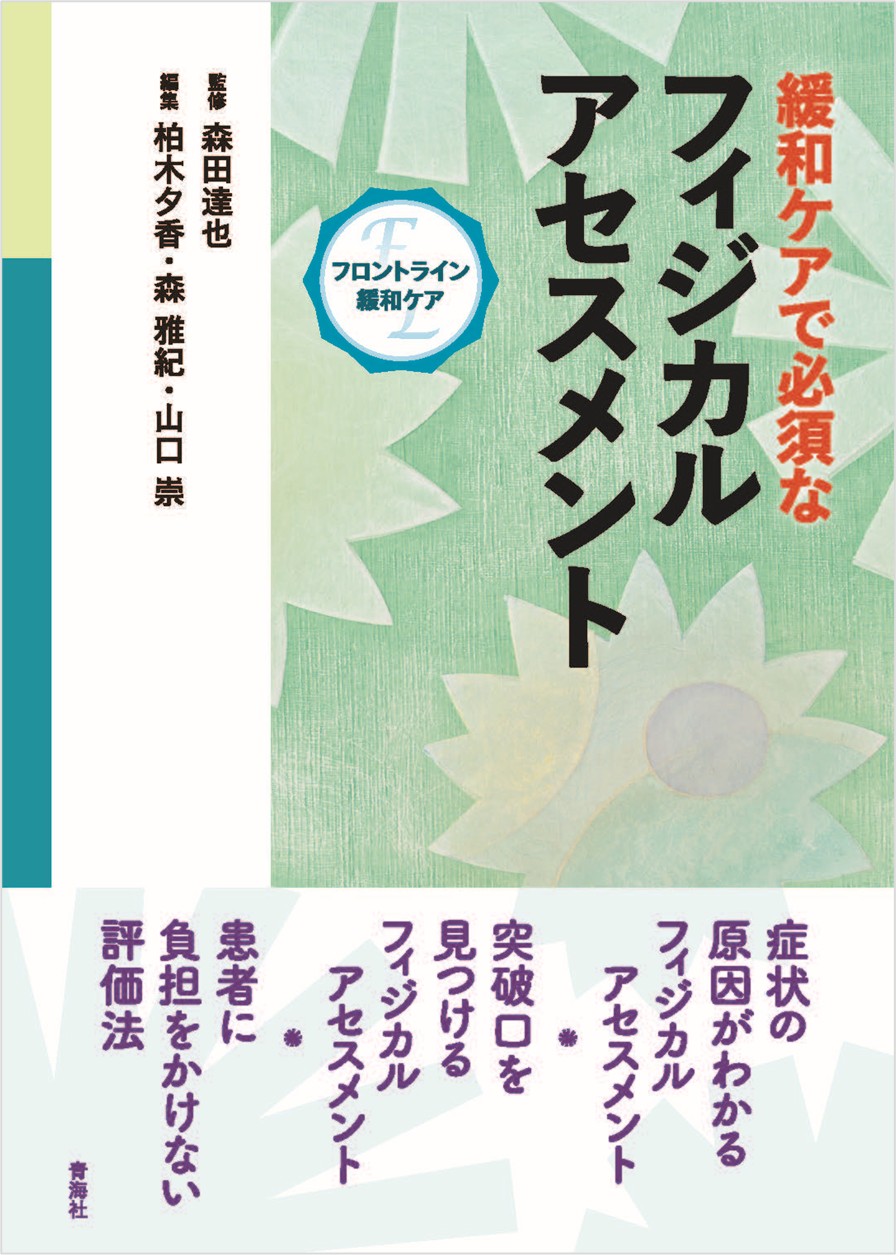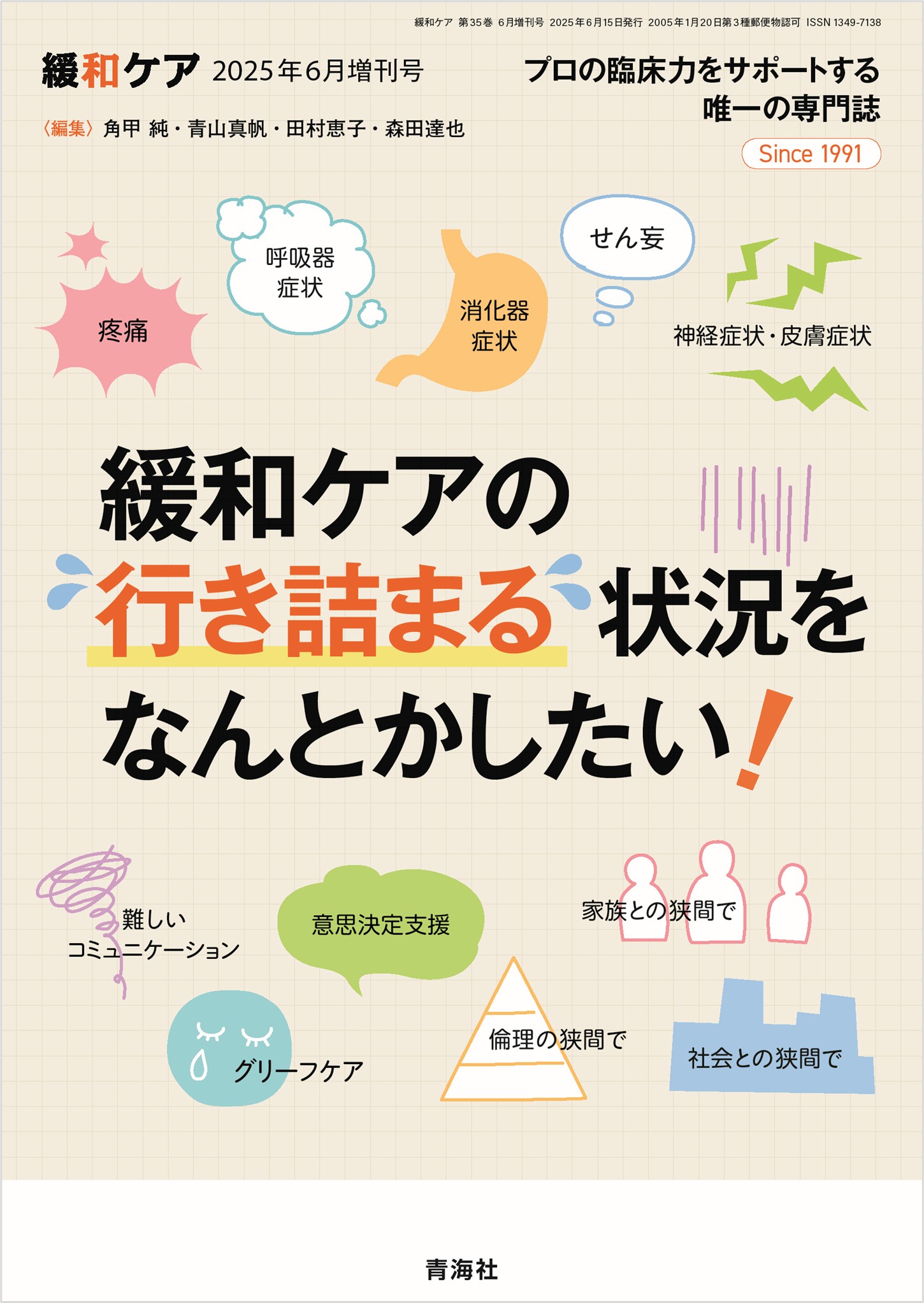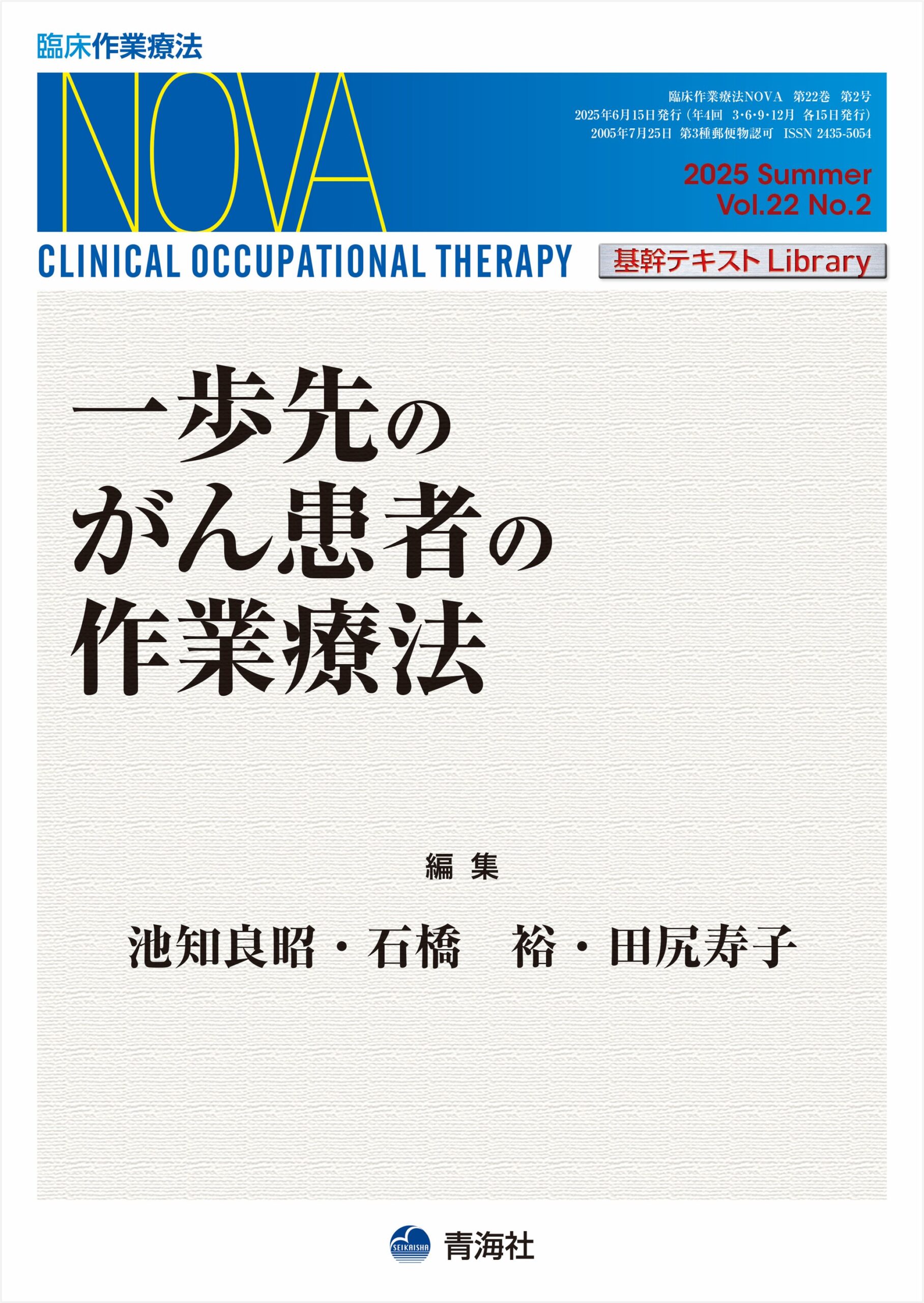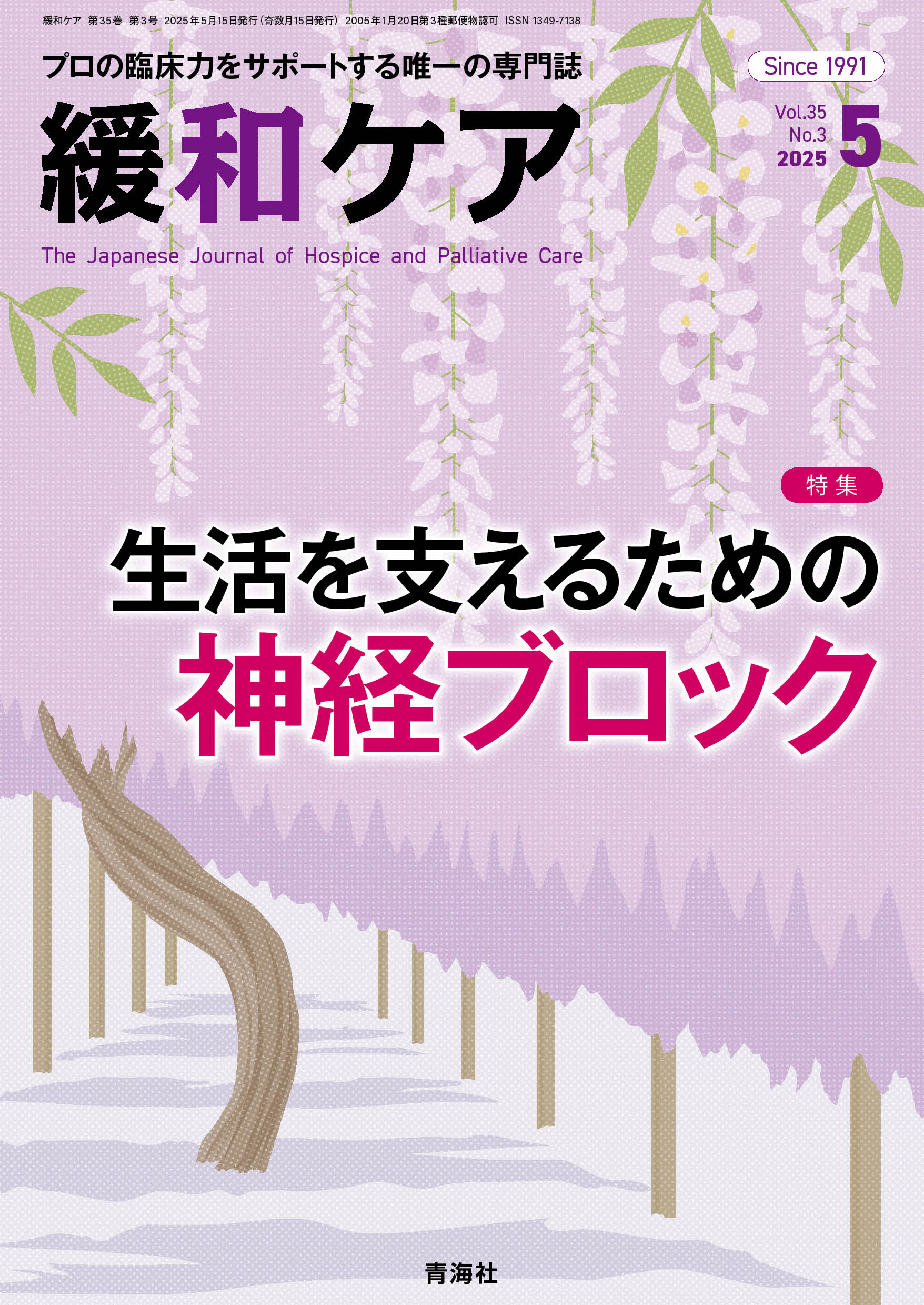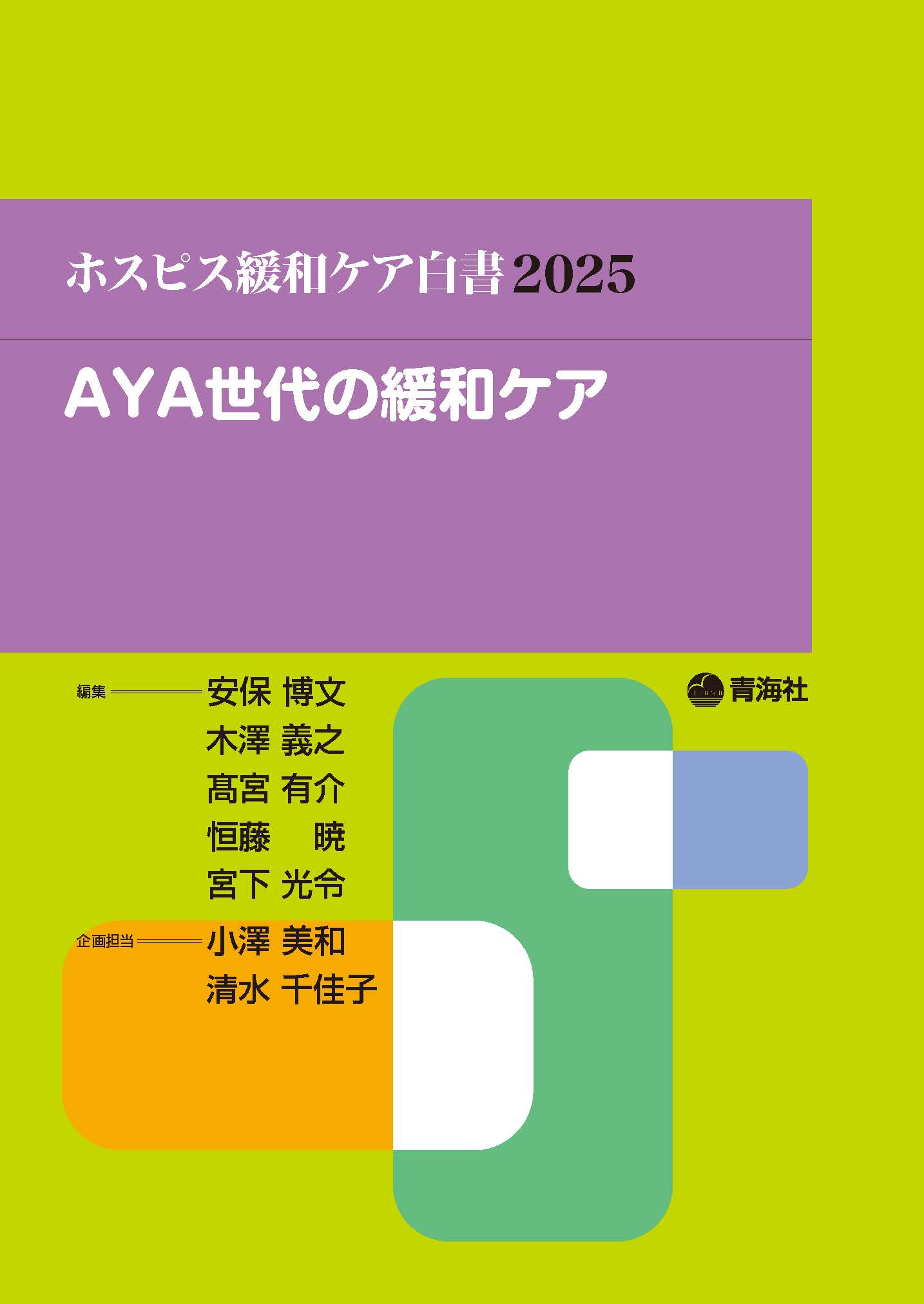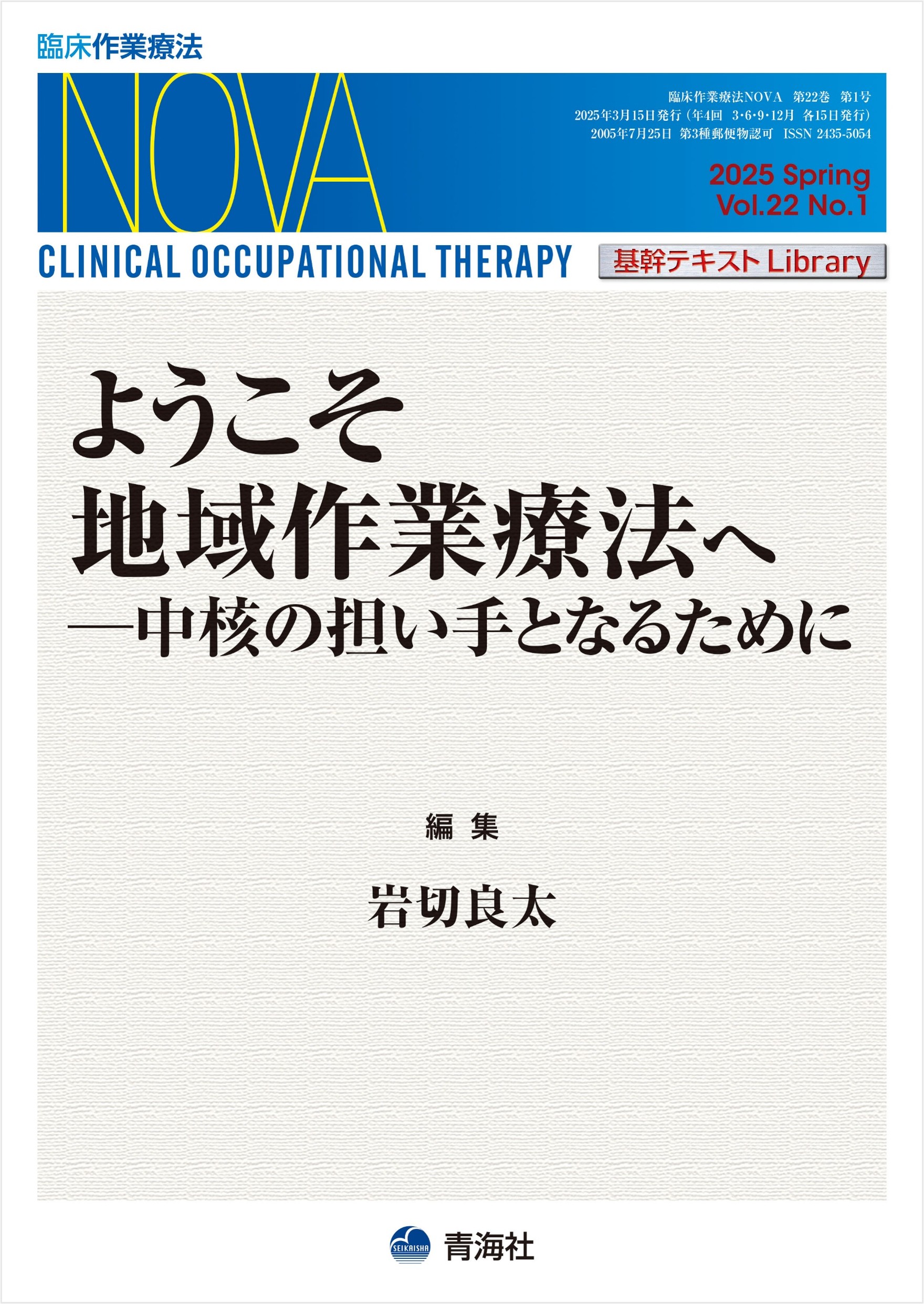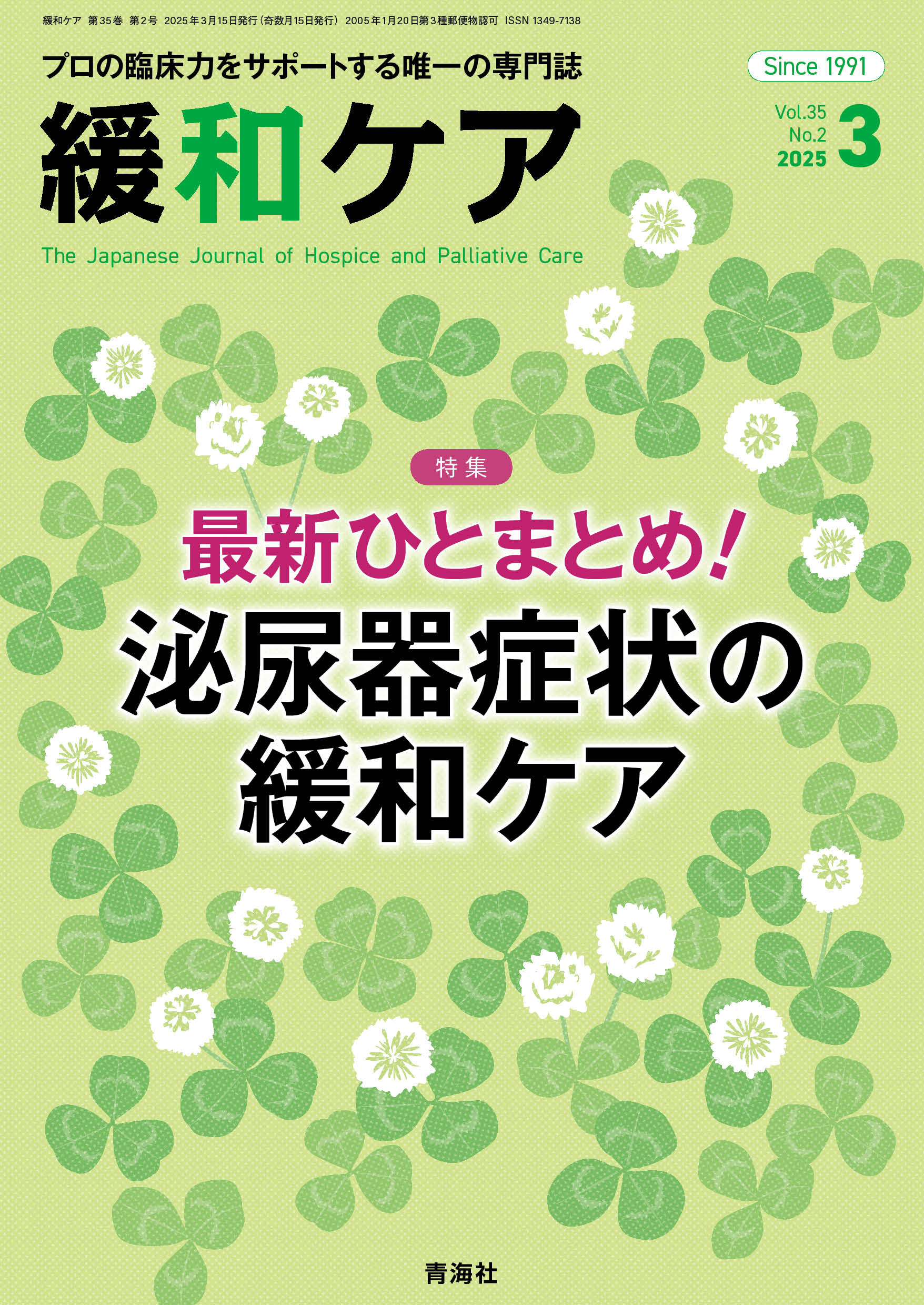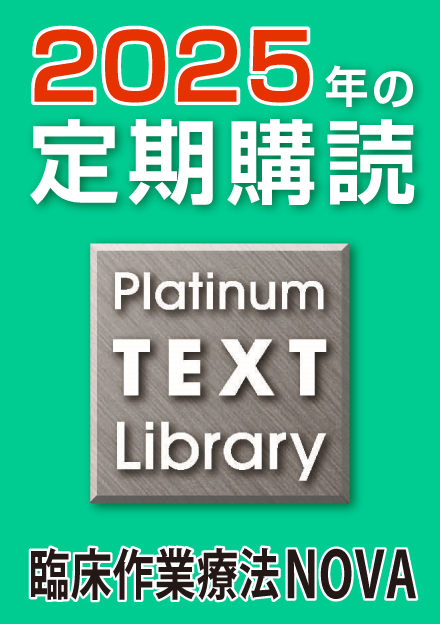目次
序文 ⅲ
第Ⅰ章 身体症状で “行き詰まる” 時
Ⅰ-1 疼痛をなんとかする
1 がん患者が「本当に痛いのか」迷う時 佐藤麻美子 002
2 手術適応のない骨折の鎮痛 櫻井宏樹 008
3 非がん患者の疼痛でオピオイド鎮痛薬レスキュー薬が欲しいと言われた時の鎮痛 笠原庸子 014
4 薬物依存や不適切使用の既往のある患者への緩和ケアにおける対応 岡本禎晃 019
5 深部に至った褥瘡の痛みのマネジメント 松原康美 024
Ⅰ-2 呼吸器症状をなんとかする
1 中枢気道内に腫瘍浸潤している患者での難治性咳嗽への一手 木村尚子 029
2 難治性呼吸困難の向き合い方─エビデンスと包括的マネジメント 萩本 聡,松田能宣 035
3 非がん性呼吸器疾患患者の治療抵抗性呼吸困難に至るまでの耐えがたい呼吸困難へのアプローチ 竹川幸恵 041
Ⅰ-3 消化器症状をなんとかする
1 副腎皮質ステロイド・消化管機能改善薬など手を尽くしても食欲が改善しない時のアプローチ 天野晃滋 047
2 胃全摘術患者や食道がん患者の上部消化管閉塞で貯まるスペースがない時のえずき 坂口達馬 053
3 環境整備やドレーンの排液を工夫しても消化器臭が気になる時のアプローチ 伊藤奈央 060
4 下剤をいろいろ試しても「下痢と便秘の繰り返し」になる便秘 中條庸子 066
Ⅰ-4 せん妄をなんとかする
ミダゾラムで鎮静できない過活動型せん妄にどう対処するか-現状を再検討し,次の一手を考える 谷向 仁 073
Ⅰ-5 神経症状・皮膚症状をなんとかする
1 薬剤性パーキンソニズムや悪性症候群への対応 宮部貴識 080
2 下肢浮腫のために日常生活活動が制限されている進行がん患者へのリハビリテーション 立松典篤 086
3 陰部(陰嚢・外陰部)浮腫に対するケア 前澤美代子 091
Ⅰ-6 その他の身体症状をなんとかする
難治性の掻痒感のある患者への非薬物的介入 毛利明子 096
第Ⅱ章 精神的ケアで “行き詰まる” 時
Ⅱ-1 難しいコミュニケーションをなんとかする
1 患者と医療者で予後の認識が大きく乖離している場合のコミュニケーション 平塚裕介 102
2 脳疾患患者の暴言・暴力・ハラスメントへの対応 山内悦子 108
3 薬の内服・投薬などの治療を拒否する人への対応 壁谷めぐみ 113
4 鎮静薬のせいで死んだのではないかと問い詰める家族 矢野琢也 118
5「自分たちでなんとかする」と支援を拒む患者家族への対応 五十嵐友里 123
6 医療者を代えてほしいと訴える患者への対応―治療関係の維持と実践課題 市倉加奈子 129
7 食・栄養に対する極端なこだわりへの対応─糖質制限,動物性たんぱく質制限,野菜中心 腰本さおり 134
Ⅱ-2 グリーフケアをなんとかする
1 若くして妻をがんで亡くした夫とその子どもへの関わり方 中西健二 140
2 家族をがんで亡くした後,何度も病院を訪れる遺族と,まったく訪れなくなる遺族への関わり方 石田真弓 145
第Ⅲ章 意思決定支援で “行き詰まる” 時
1 未成年の子どもをもつがん患者から「子どもにどのように伝えたらいいのかわからない」と相談されたら 赤川祐子 152
2 「Make a Wish」を勧めるタイミング 津村明美 158
3 余命が短い患者の不確かさを軽減し,希望を見出す 中野貴美子 163
第Ⅳ章 患者を取りまく事情で “行き詰まる” 時
Ⅳ-1 家族との狭間の状況をなんとかする
1 鎮静の開始を希望する患者と,開始しないでほしい家族 阿部晃子/日下部明彦/佐伯玲菜 170
2 患者の意向に関係なく未告知を希望する家族とのコミュニケーション 竹下隼人/石上雄一郎 176
3 医師と看護師の間で言うことや態度が異なる患者 髙橋紀子 181
Ⅳ-2 倫理の狭間の状況をなんとかする
1 患者や家族が民間療法や代替治療をどうしてもと希望したら 西村瑠美/石木寛人 186
2 患者は吸痰を希望するが,苦しそうなのでと,家族が吸痰をしないでほしいと言う場合 佐々木理衣 191
Ⅳ-3 社会との狭間の状況をなんとかする
1 矯正医療施設(医療刑務所)における緩和ケア(文献考察)─刑務所の現場で問う“人間らしさ” 大谷弘行 196
2 重症心身障害を抱える人への緩和ケア 河俣あゆみ 201
3 セクハラへの対応と予防─組織的対応と目標志向型の看護実践 細川 舞 207
4 家族力を期待できない患者の退院支援を困難にさせている正体とは─問題と課題を区別した捉え方とアプローチ 宗好祐子 213
5 “LGBTQ+”に対して知っておくべきこと 厚坊浩史 218